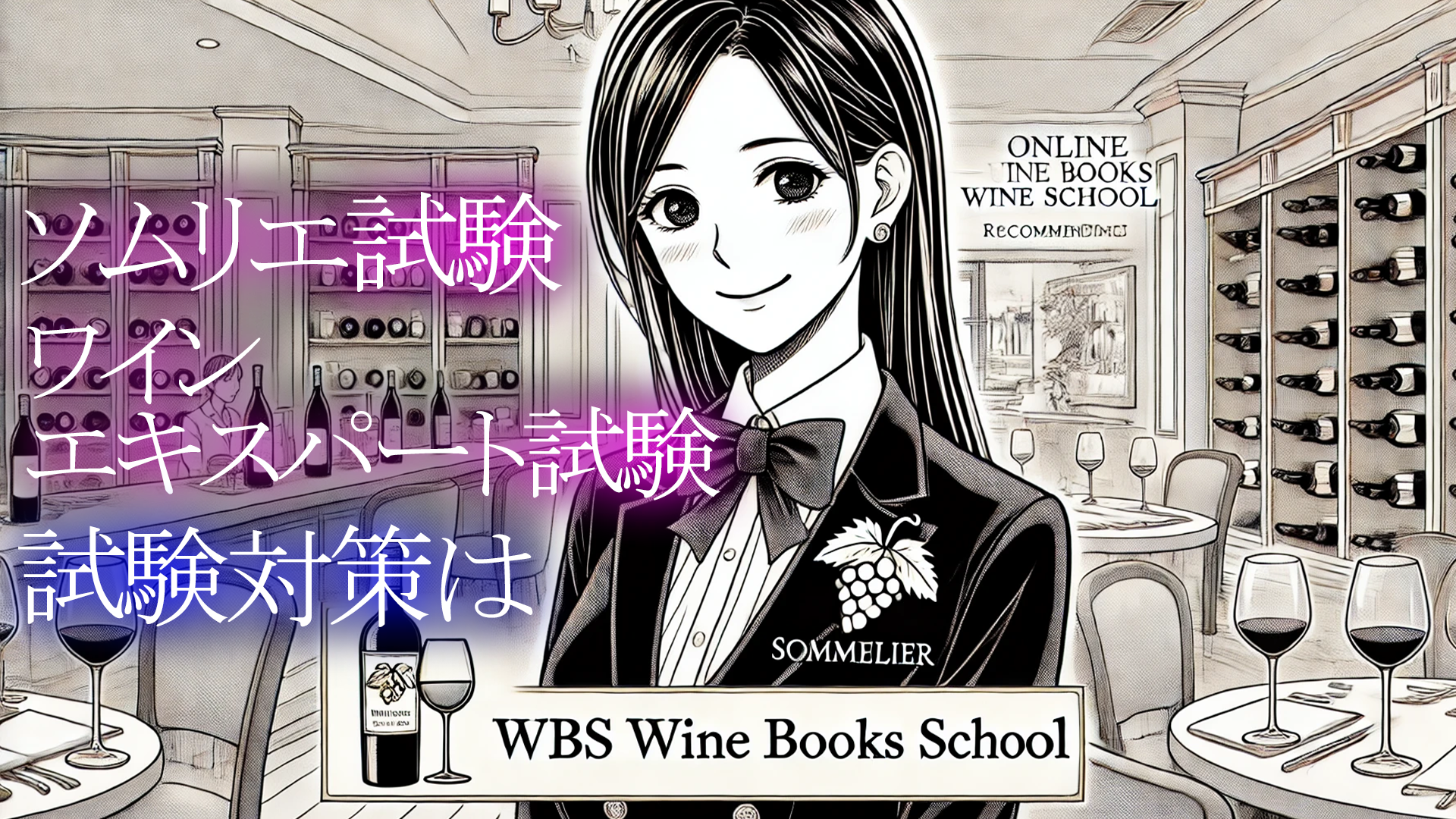ワインの賞味期限|ワインボトルに賞味期限がない?消費期限との違いは?
スーパーやワインショップでワインを手に取ったとき、「これって賞味期限ないけど大丈夫?」と不安になったことはありませんか?
他の食品には当たり前のように書かれている“賞味期限”ですが、ワインには記載されていないものがほとんど。
実はそれには、ワインという飲み物ならではの理由があるんです。
この記事では、「ワインに賞味期限はあるのか?」という疑問に対して、食品表示のルールやワインの熟成・保存の考え方を交えて、わかりやすく解説していきます。
初心者がつまずきがちなテーマを、プロの視点でスッキリ整理してみましょう。
動画でも解説しています
ワインの賞味期限|賞味期限はあるの?消費期限との違いは?
ワインの賞味期限は表示義務なし
ワインにはなぜ賞味期限の表示がないのか?――その理由は、ワインが「酒類」として食品表示基準における表示義務の例外とされているからです。
日本では、食品の表示ルールは「食品表示法」に基づいて定められており、その中に賞味期限や消費期限の表示に関する詳細な規定があります。
しかし、アルコール分が10度以上の酒類については、保存性が高く衛生上の問題が生じにくいため、賞味期限の表示義務が法律上免除されているのです。
ワインはこの「酒類」に分類されており、腐敗や食中毒のリスクが極めて低いため、基本的に賞味期限を記載する必要はありません。
ただし、これは「いつまでも美味しく飲める」という意味ではなく、ワインの種類や保存環境によって品質は変化します。
賞味期限の表示がないからこそ、適切な保存と飲み頃の判断が重要になるのです。
賞味期限と消費期限
私たちが日頃目にする「賞味期限」と「消費期限」。この2つは似ているようで、法律上は明確に区別されています。
日本では「食品表示基準」(食品表示法に基づく)により、それぞれの意味と表示ルールが定められています。
賞味期限は、適切に保存した場合に「美味しく食べられる期限」を示すもので、多少過ぎてもすぐに食べられなくなるわけではありません。
スナック菓子や缶詰、チョコレートなど保存性の高い加工食品に使われます。
一方、消費期限は「安全に食べられる期限」を意味し、期限を過ぎると衛生上のリスクがあるとされます。
お弁当、惣菜、生クリームなど、傷みやすい食品が対象です。
つまり、賞味期限は「品質」、消費期限は「安全性」を示す指標です。
どちらも消費者の安心のために欠かせない情報ですが、その性質を理解して使い分けることが大切です。
ワインについては酒類に該当するため義務規定の例外になっていますので、賞味期限も消費期限もどちらも表示義務はありません。
実質的な賞味期限「美味しく飲める期限」はあるのか?
ワインに賞味期限の表示はありませんが、「いつまで美味しく飲めるか」という意味での“実質的な賞味期限”は存在します。
特に重要なのが、「開ける前にどれだけ美味しさを保てるか」という視点です。
一部の高級ワイン、たとえばフランス・ボルドーやイタリアのバローロなどは、熟成を前提に造られており、数年〜数十年のスパンで“飲み頃”を迎える設計になっています。
こうしたワインは、年数が経つことで風味が複雑になり、真価を発揮します。
一方で、スーパーや酒屋で手に入りやすい低価格帯のワインは、ほとんどが“早飲み”を想定して造られています。
これらは出荷された時点ですでに飲み頃に達しており、購入後1〜2年以内に楽しむのがベスト。
長く置くと、風味が落ちたり酸化が進んだりするリスクがあるため、あくまで“今が美味しい”と考えておくとよいでしょう。
実質的な消費期限「開けた後」問題
ワインは未開封であれば長期保存が可能な飲み物ですが、一度開栓すると品質の変化が急激に進みます。
空気に触れたことで酸化が始まり、香りや味わいが徐々に劣化していくのです。
この状態が進みすぎると、風味が損なわれるだけでなく、実質的な「消費期限」、つまり飲まない方がよい安全上のリミットが生じます。
ワインにはアルコールが含まれているため腐敗のスピードは比較的遅いものの、酸化によって酸っぱくなったり、雑菌が繁殖して酢のようなにおいがしたりすることがあります。
これが進むと、お腹を壊す可能性や体調不良を招くリスクもゼロではありません。
一般的に、開けたワインは赤なら3〜5日、白やロゼは2〜3日、スパークリングはその日中が美味しく飲める目安です。
味やにおいに明らかな異変を感じた場合は、無理せず処分するのが賢明です。
まとめ
ワインには賞味期限や消費期限の表示がありませんが、実際には「美味しく飲める期間」や「飲まない方がいいタイミング」が存在します。
開ける前のワインは、保存状態に問題がなければ急激に劣化することは少なく、特に早飲みタイプのワインであれば、出荷から1〜2年程度は美味しく楽しめます。
一部の高級ワインに至っては、熟成によって風味が深まり、10年以上先に飲み頃を迎えることもあります。
このように、未開封の状態では“実質的な賞味期限”は比較的緩やかに訪れるのが特徴です。
一方で、開けた後のワインは様子が一変します。
空気に触れた瞬間から酸化が始まり、味や香りがみるみるうちに変化。数日以内に飲み切らないと、風味が損なわれるだけでなく、場合によっては体に悪影響を与える可能性も。
つまり、開栓後のワインには“実質的な消費期限”が早く訪れると言えるのです。
【ワインブックスオンラインスクールのご案内】

このサイトは、ワインブックススクールの運営です。
ワインブックススクールでは、月額2200円で、いつでも、どこでも、誰でもワインの学習ができる環境が整っています。
ソムリエ・ワインエキスパート試験の対策に
趣味のワインライフに
エクセレンス試験の対策に
飲食店の頼もしい見方に
ご活用ください。必ずお役に立てることをお約束します。
WBSのソムリエ・ワインエキスパート試験対策講座はこちら→
毎月届くブラインドテイスティングのサブスクリプションサービス
全国どこでも受講できるブラインドテイスティングの通信講座もお勧めです→
ソムリエ・ワインエキスパート試験の効果的な勉強方法
62ステップで無料公開の記事はこちら→