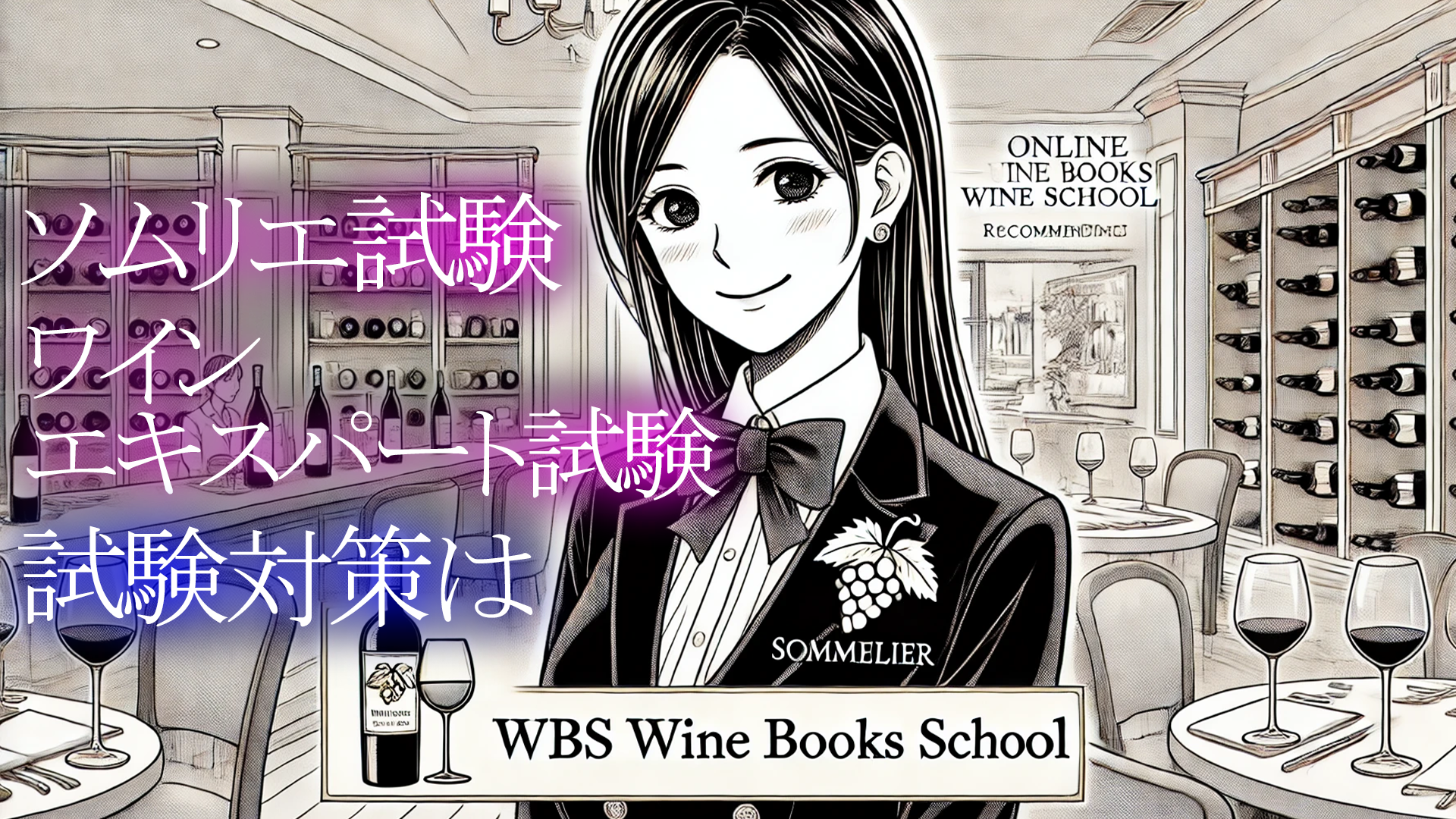ワインの表現方法「飲みやすい」はなぜ禁句レベルのNGなのか?
ワインを飲んだとき、つい「これ、飲みやすいね!」と言ってしまったことはありませんか?
実はこの「飲みやすい」という表現、ワインの世界では少し注意が必要な言葉です。
一見するとポジティブな感想のように聞こえますが、場面や相手によっては「この人、ワインのことをあまり分かっていないな」と思われてしまうこともあるのです。
なぜなら、ワインは「個性」や「違い」を楽しむ飲み物だからです。
酸味、渋み(タンニン)、果実味、ミネラル感といった要素が絶妙に絡み合い、そのバランスや変化を味わうのがワインの醍醐味。
しかし「飲みやすい」という言葉は、これらの要素を無視してしまいがちで、ワインの奥行きや魅力をきちんと捉えていない印象を与えてしまいます。
特に、丁寧に造られた高品質なワインほど、最初の一口でスルスル飲めるだけでは語れない奥深さや複雑性を持っています。
そんなワインに対して「飲みやすい」とだけコメントしてしまうと、せっかくの魅力を見逃しているかのように受け取られかねません。
今回は、なぜ「飲みやすい」という表現がワインを語るうえで危険なのか、そしてどう表現すればもっとワインを楽しめるのかを詳しく解説していきます。
【動画でも解説しています】
ワインの表現方法「飲みやすい」はなぜ禁句レベルのNGなのか?
高品質なワインは個性やストーリーが大事になる
ワインを深く知れば知るほど気づくのは、「高品質なワインほど個性とストーリーが重要になる」という事実です。
単に味が整っているだけでは、本当に良いワインとは言えません。
産地の特徴、ブドウの育った土壌、造り手の哲学や想い――そうした背景すべてが、ワインの一滴一滴に宿っています。
高品質なワインは、飲み手にただの「美味しさ」以上のものを求めます。
それは、なぜこの味わいになったのか、どんな気候や土地、どんな造り手の工夫が隠れているのかという“物語”への共感です。
ボルドーの格付けシャトーや、ブルゴーニュの小さなドメーヌ、イタリアの伝統的な生産者たち。それぞれに歴史と誇りがあり、その背景を知れば知るほど、一杯のワインが何倍にも味わい深く感じられるのです。
つまり、高品質なワインは「飲み手の感受性」を試しているとも言えます。
どれだけそのワインの個性を受け止め、背景に思いを馳せられるか。それが、ワインの本当の楽しみ方なのかもしれません。
「飲みやすいワイン」はマス向けワインへの誉め言葉?
「飲みやすい」という言葉は、ワインを褒めるときによく使われます。
しかしこの言葉が本当にフィットするのは、実は低価格帯のワイン(マス向けワイン)に対してのケースが多いのです。
飲みやすいとは、ワイン単体でスルスルと喉を通る、クセが少なく引っかかりがないという意味。
つまり、誰でも抵抗なく楽しめる設計がされているワインへの素直な賛辞といえます。
一方で、料理と合わせて楽しむ本格的なシーンでは事情が変わります。
ワインは食事と一緒に楽しむことで真価を発揮する飲み物。
料理と合わせるなら、ある程度の酸味や渋み(タンニン)がある方が、食材との一体感やコントラストを生み出し、より深いマリアージュを楽しめます。
特に高品質なワインほど、単体では少し硬かったり酸が立っていたりするもの。
それは、料理と合わせたときに初めてバランスが完成するよう計算されているからです。
つまり、「飲みやすい」=常に良い評価とは限らないということ。
ワインを楽しむ場面や目的によって、求められる個性は変わってくるのです。
そのほかの禁句レベルキーワード
ワインの場では、気をつけたい禁句ワードがいくつかあります。
その代表例が「飲みやすい」「バランスがいい」「美味しい」という表現です。
一見、どれもポジティブな印象を持つ言葉ですが、実はこれらはすべて主観的すぎるため、正式なワインファンの集まる場では使わない方が無難とされています。
「飲みやすい」は個人の感覚に強く依存し、具体的な味わいや構成を伝えられません。
「バランスがいい」も、どの要素とどの要素がどう釣り合っているのかを説明しなければ、単なる感想止まりになります。
そして「美味しい」は、ワインの特徴ではなく、自分の好みを表明しているだけにすぎません。
こうした主観的なワードは、ワインそのものを客観的に表現する能力が問われる場では、知識や経験が浅い印象を与えてしまうリスクがあります。
特に、テイスティング会やワインスクール、専門的な場では、より具体的に「果実味が豊か」「酸が伸びやか」「タンニンが繊細」など、ワインの構成要素を踏まえた表現を心がけることが求められます。
ワインを楽しむだけでなく、しっかりと語れるようになるためには、言葉選びこそが大切なのです。
親しい間柄では禁句ワードは全く問題なし!
このように、ワインを語るとき、主観的な言葉は避けた方がいいと言われることがあります。
確かに、テイスティング会やプロフェッショナルな場では、できるだけ客観的な表現が求められます。
しかし、家族や友人など、すでに親しい間柄であれば、実はそこまで神経質になる必要はありません。
親しい人たちとのワインの時間は、何よりも「一緒に楽しむこと」が目的です。
このとき、「美味しいね」「飲みやすいね」といった感想レベルの言葉でも、十分に気持ちは伝わります。
むしろ、あまりに堅苦しい表現をすると、場の空気を壊してしまうことさえあります。
大切なのは、相手に自分の感動を素直に伝えることです。
ワインの個性を細かく分析するよりも、「これ好き!」「すごく華やかだね」といった一言が、場をあたたかく、楽しいものにしてくれます。
場面に応じて、言葉の使い方を柔軟に変えること。これも、ワインを楽しむうえでの大切なセンスと言えるでしょう。
まとめ:重要なのは、「何を言うか」ではなく「どう伝わるか」
ワインを表現するとき、使う言葉は「誰と飲んでいるか」で大きく変わります。
同席している相手のワインへの理解度によって、適切な言葉選びが求められるのです。
初心者や親しい友人との場であれば、「美味しい」「飲みやすい」といった主観的な言葉で十分に気持ちが伝わります。
しかし、プロやワイン愛好家が集まるような場では、より具体的で客観的な表現が必要になります。
ワインの香りや酸、果実味、タンニンの質感など、特徴を的確に伝えることで、相手に信頼感や共感を生み出せます。
大切なのは、「自分が何を知っているか」ではなく、「相手にどう伝わるか」を意識すること。
相手に合わせた言葉選びができれば、ワインを通じたコミュニケーションもさらに豊かになるでしょう。
【ワインブックスオンラインスクールのご案内】

このサイトは、ワインブックススクールの運営です。
ワインブックススクールでは、月額2200円で、いつでも、どこでも、誰でもワインの学習ができる環境が整っています。
ソムリエ・ワインエキスパート試験の対策に
趣味のワインライフに
エクセレンス試験の対策に
飲食店の頼もしい見方に
ご活用ください。必ずお役に立てることをお約束します。
WBSのソムリエ・ワインエキスパート試験対策講座はこちら→
毎月届くブラインドテイスティングのサブスクリプションサービス
全国どこでも受講できるブラインドテイスティングの通信講座もお勧めです→
ソムリエ・ワインエキスパート試験の効果的な勉強方法
62ステップで無料公開の記事はこちら→